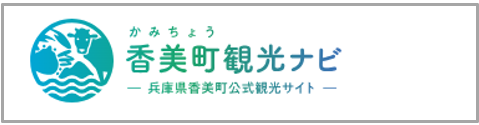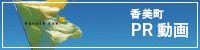凪。時に激しく荒れる海が穏やかになり、風も静まる穏やかな時間。海面はその日の空をそのままに映し、一瞬の静寂が時を止める。海と共に生きる漁師たちは、絶好の漁日和と海に繰り出す。
香美町の中でも漁師町として知られる香住区。ここで生まれ育った女性が、その好天気の名前を受けた食堂をオープンした。「柴山みなと前食堂 凪」オーナーの寺川和美さん。2016年11月にオープンした食堂には、地域の内外から幅広い世代のお客様が訪れ、話に花を咲かせる。
ふるさと香住でみつけた「私にできること」
「子どもの頃していた遊びはもちろん、海で泳ぐこと。それに、醤油を海に持って行ってウニを割ってその場で食べるとか(笑)」
子どもの頃の思い出の片隅にはいつも海があり、柴山漁港があったと語る寺川さん。遊び方もダイナミック、レジャーを求めなくても多彩な楽しみ方が見いだせた。
高校卒業後には、調理師学校へ進学するため離れた故郷・香住。その後神戸の飲食店等で経験を重ね、久しぶりに帰ってきた故郷に思ったのは、
「寂しいな。みんなで集まれるようなお店がほとんどない」
ということ。故郷に帰り似たような心境になる地方出身者は少なくないだろう。ただ寺川さんはただそれを思うだけでなく、
「私自身が、不平不満を言うだけではおさまらないタイプなので。何とかしたいな、自分にできることはないかな、何かできることがあるんじゃないか」と考え、行動し始めた。
「生まれ育った場所だけど、香住・柴山で働いている人はほとんどいない。地区外や町外に出て働く人が多いから、地元でのつながりが生まれにくいなと思って、人と人が出会って繋がれるような場所があったら面白いな、と考えました」

背中を押してくれた、隠岐の島での出会い
不足を不足で終わらせず、「できること」を模索し始めた寺川さん。ただ準備を進めながらも、気持ちの中では「本当に起業なんてできるのかな」という迷いがぬぐえなかったという。
「そのメンタルを鍛えるために、ひと夏の間隠岐の島のゲストハウスのお手伝いをしました」
その出会いが寺川さんの追い風になった。ゲストハウスのお客様と一緒にご飯を作り、一緒にご飯を食べる。出会った人と食を囲む機会は寺川さんに改めて、自らがかかわり続けていた「食」が人と人とをつなげることを再確認させてくれたという。
「そこの女性オーナーも、力まずに経営をしていて、それを見て『起業って大それたことのように思っていたけど、全部完璧じゃなくてもいいや』と思えました。とりあえず、私にできることをやってみて、あとはやりながら考えたらいいかなって。同じような、女性で起業した人に出会えて本当に心強かったんです」
思い立った寺川さんにタイミングが味方する。いい物件の情報も入り、ご両親のサポートも受けながら即決。
「何か知らんけど、不安とか二の足とかなかったんです。『やる!』『きっと大丈夫!』一色になっちゃって。行動し始めたら、後戻りできなくなったというのもありますね(笑)。もちろん、周りのサポートも必要だし、お願いすることもいっぱいありました。地元の方々にもいろいろと協力していただきました」

起業はしやすかったと語る寺川さん。広いフィールドがあり、手つかずの場所や分野も多いからこそ、「自分ができるもので産業を始めたら、うまくいくような土地だと感じています。まだまだこれからのまちだから、様々な分野のお店やお仕事が生まれたら」と後に続く人を期待もしているという。
「凪」が人と人とをつなぐ場所であるように

「隠岐の島で本当にいい出会いがあり、『このまま住んでもいいかな』と思ったこともありました。でも、人生の節目、何かあるたびに帰ってきたいと思うのはなぜか、故郷の香住だったんです」
無条件にある、「生まれ育った場所だから」こその香住への想い。寂れていくまちに人が集まる場所をと「凪」をオープンしたことで、「地元の人たちは、『ようやった』みたいに言ってくれます。お野菜や魚を頂いたり、『頑張ってるか』って見に来てくれたり。はじめは『変わったことをしてる』って思われるんじゃないか不安もあったたんですけど、可愛がっていただけてるので」さらなるやる気がわいてくると、寺川さんは笑顔を見せる。
外から来た人にも開かれて、中の人たちも仲良く集まれる場所。真面目な話も大切だけれど、ゆるい空間の中で出る話の中には光るアイディアが眠っていることもある。
「凪がオープンして半年たったんで、そういう場所にできたらいいなって思ってます。漁師さんもたまにお店に来てくれるし、漁業に興味を持つきっかけになったりしてもうれしいなって」
お店を持っていなかったら出会えなかったような人と、たくさん出会えた。そのことが一番の喜びだと話す寺川さん。地区の内外の人が集まり、食を囲むことで繋がれる場所としての「凪」の可能性を、楽しみながらも模索し続けている。
「完璧でなくてもいい。自分のできることをすれば、うまくいく」
寂しくなった故郷をただ嘆くだけでなく、その中で「わたしにできること」を模索し続けた寺川さん。未開拓のフィールドを思うように使い、実現する、その土壌が、香美にはある。












.jpg)